002
昭和14年中国地方調査ノート その1 クグシ・品種改良・山林ノ統一
資料紹介|2025年4月15日|板垣優河
中国地方調査ノートの分析
宮本常一記念館(以下、当館)では、昭和14(1939)年11・12月に宮本が中国地方で作成した調査ノートを6冊保管している。この調査は、宮本がアチック・ミューゼアム(後の日本常民文化研究所)に入って最初に行った本格的な民俗調査である。宮本は11月16日に東京を立ち、まず島根県八束郡恵曇村(現松江市鹿島町)をはじめとする八束半島の漁村を歩いた。続いて江津から邑智郡田所村(現邑南町)を訪ね、さらに山を越え、広島県山県郡大朝町(現北広島町)、同郡八幡村(同前)、戸河内町(現安芸太田町)、島根県美濃郡匹見上村(現益田市匹見町)、山口県玖珂郡高根村(現岩国市錦町)と、中国山地の脊梁筋を歩き、12月4日に岩国に出た。一連の調査の報告は、『出雲八束郡片句浦民俗聞書』(宮本1942)、及び『中国山地民俗採訪録』(宮本1976)においてなされている。また『村里を行く』に収められた「土と共に」は、この調査の紀行文であり、併せて読むことで調査の周辺をうかがい知ることができる(宮本1943)。さらに近年、当館では調査ノート6冊の翻刻と印刷製本を『宮本常一農漁村採訪録』第26・27巻において行った(板垣編2024・2025)。これにより、中国地方で営まれていた農山漁村の暮らし、山野河海での生産活動の輪郭を捉えることが可能になった。
ところで、筆者の専門は考古学であり、縄文時代の植物採集活動について、民俗学的な手法も援用しながら研究を進めてきた(板垣2024)。その観点から宮本の資料を紐解くと、それらが自身の調査記録と対照させ、民俗事象の時期的推移や地域的差異をみるうえで、誠に有用度の高いものであることに気付く。
宮本に関する書籍はこれまでにも優れたものが出ている。しかし、その多くは既に公刊されている宮本の著作を基軸にして展開する評伝であった。これに対し、当館がもつ強みは、宮本が民俗調査に際して作成した一次資料というべきものを多数保管していることである。そこには農山漁村の生活文化が、あるいは著作以上に克明に記録されているかもしれない。筆者としては、当館で保管している資料の観察と分析を通して、宮本の仕事の学問的な魅力と日本文化の特質をともに探っていきたいと考えている。特に中国地方の調査ノートは、上記の筆者自身の調査課題に加え、採訪地域が地理的に近いという理由から、周防大島の生活文化を見ようとする際に、重要な比較検討材料になると思われる。
以下、筆者はそうした趣旨のもと、いくつかの項目を立てて中国地方の調査ノートを分析していく。なお、中国地方の調査ノート6冊の表題と目録番号はそれぞれ次のとおりである。
・「片句年中行事」(2-2/0059/01/00)
・「中国2 片句聞書 市山、田所聞書」(2-2/0060/01/00)
・「中国3 鱒渕」(2-2/0061/01/00)
・「中国4 田所、大朝、八幡、樽床」(2-2/0062/01/00)
・「中国5 樽床、横川、三葛、高根」(2-2/0063/01/00)
・「中国6 高根村聞書」(2-2/0064/01/00)
先述のように、これら資料はすでに『宮本常一農漁村採訪録』第26・27巻として印刷に付している(板垣編2024・2025)。前半3冊のノートは26巻、後半3冊のノートは27巻に収録している。以下の資料提示では、原則としてそこからの引用という形式で行うものとする。なお、文中の[/]は改行のあることを示す。
クグシ・品種改良・山林ノ統一
宮本は昭和14(1939)年11月28日に広島県山県郡八幡村(現北広島町)を訪れた。その日は雪が降り積もっていた。『村里を行く』の「土と共に」では、「八幡の高原は殊更に雪が深い。蕭條たる野に点々と家がある。烏がとび立つては下り、おりてはとび立つているのが見える。全くひつそりした冬の村である」と書いている(宮本1943:233)。調査ノートには、「柿ガアカクナラヌ。青イママニ冬ガ来テクロクナル。[/]桑モ大キクナラヌ。カヒコハ一回ダケシカカヘヌ」とある(板垣編2025:35)。高冷地特有の生活条件の厳しさがうかがえる(写真1)。
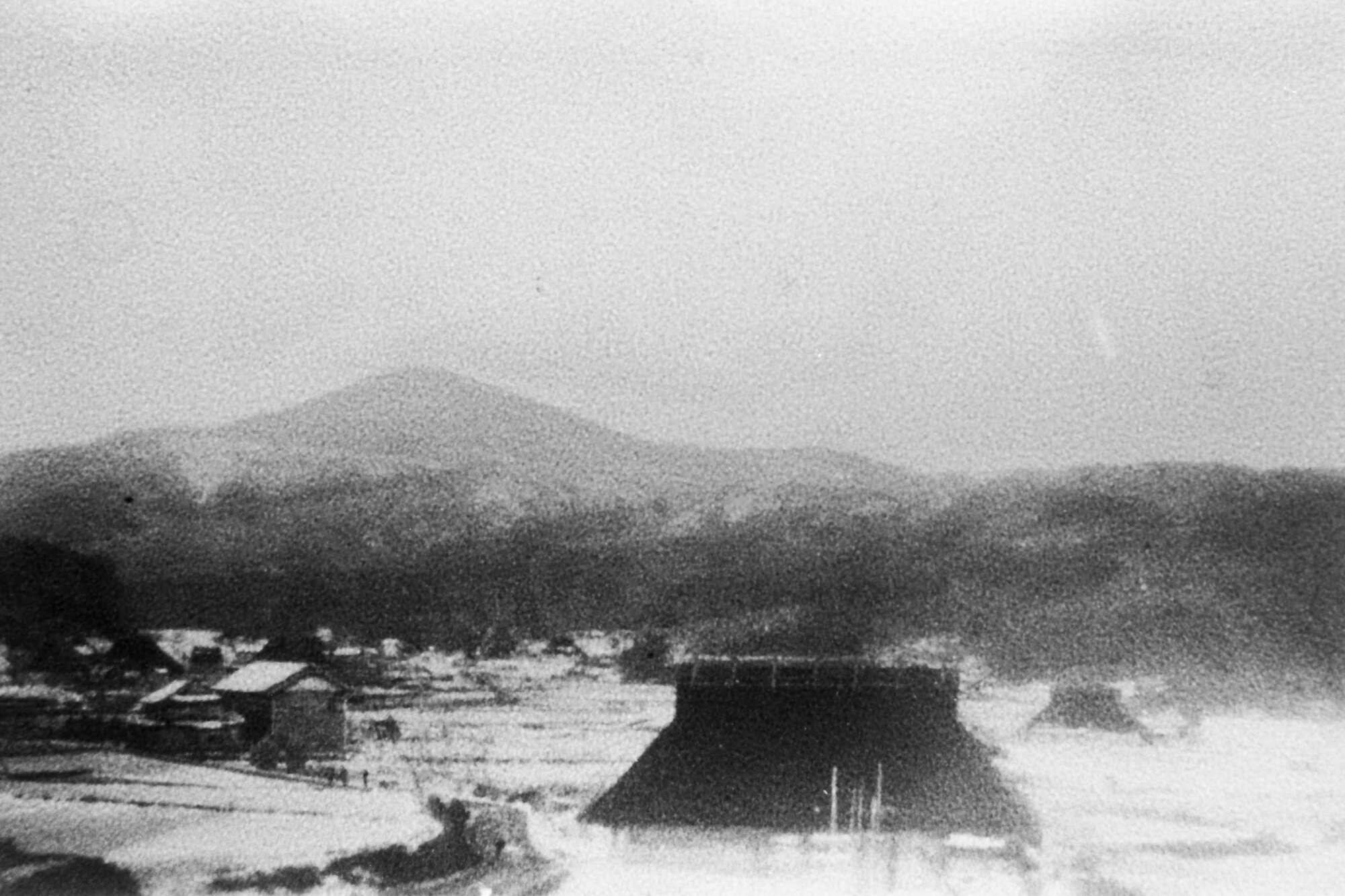
この村では早霜によって稲が稔らずに黒く枯れてしまうことがあった。それを防ぐために、「クグシ」と呼ぶ作業が行われていた。調査ノートには「秋彼岸頃ニナルト急ニヒエテ、シモノオリルコトガアル。[/]スルト稲ガダメニナルノデ、村デハ番小屋ヲツクツテ交代デ見張ヲナス。シモガオリサウダトオモフト、村人ヲカリ出シテ青柴ヲイブシ、キリガオリタ位マデニクグス。[/]スルトシモニナラナイデスム。10月半マデ之ヲ行フ」とある(同前:34)。「クグシ」とは「クブシ」、すなわち「燻ぶらせる」という意味である。
クグシについて、宮本はさらに詳しく聞いている。調査ノートには次のように書かれている。「明治33年ニシモガハヤクオリテ、34年カラハジメタ。[/]ソレ以来タヤサヌ。[/]明治ノハジメノミノトシニハ、早クシモガオリテイネモミノラズ。[/]サル年ハウンカガワイテガシンニナリ、餓死シ、ソノウエヤク病ハヤリ、タルトコ三分二マデ死ンダ。[/]ミノ年ノキキンニハ、シモガハヤカツタ。[/]明治33年ニモシモノ害アリ。ヤワタノゴーアタリデハ、ミナシイラニナツタ。[/]1俵ノモミデ、一斗ノコメデアツタ。[/]シナノ[信濃]デ、クハ[桑]ノメヲフセグノデ、クグシヲスルトイフノヲキイテ、スルコトニナツタ。[/]明治34年、クグシヲシタ。ソレカラハジメタ。[/]カイセイニナツテ、ユービンノ出来タノト、クグシガヨイト、トシヨリガイツタ。[/]二反ニ一ケ所グライクグシヲシタ。[/]バンゴヤヲタテテ、セイネンガ番ヲシタ。近頃各戸ジユンバン。[/]60[戸]ヲ三クミニシ、1組2人、計6人ヅツデバンヲスル。[/]クグシノハジマルマヘニ、木ハジユンビシテオク。[/]大キナタバニシテオキ、上ニモミガラナドカケテオク。[/]下カラ火ヲカケル。[/]濃霧ニナツタヨウデアル。[/]毎年ヤツテイル。[/]彼岸ヲスギテハジメ、10月一杯ヤル。[/]刈上ゲヲオハルマデヤル。ソノアイダニ、二晩カ三晩位ノモノデアル」(同前:48)。
村人は田のほとりに番小屋を設けて交代で番をし、霜が降りそうな夜には村人総出で田の周囲で青柴を燃やし、冷気を和らげた。そうした作業を明治34(1901)年から毎年やっていたという。
また、山間で作られていた稲にも品種改良がみられた。調査ノートには「オク山ノ米ハクサイトテ相手ニセラレナカツタ。ネガ安カツタ。[/]ソレハ品種カラ来タモノトイフコトニナツタノデ、陸羽モノヲモツテキタラヨク出来テ、クサミガナクナツタ」とある(同前:48-49)。米の品種が悪く、周囲から軽蔑される風もあったようだが、冷害に強い東北系の品種がもたらされ、臭みがなくなったという。霜害もさらに解消されていったものと思われる。
こうしたことから、山間の暮らしも少しずつ良くなっていったようである。調査ノートには「八幡ノ村ノコエル事業ハ、クグシ、品種改良、山林ノ統一」と書かれている(同前:49)。
「山林ノ統一」とは、山林を村の共有財産にしたという意味である。調査ノートにはその経緯が次のように記されている。「明治41年1月、加茂郡川上村デ二宮報徳社ノ出来タノガシンブンニ出テイルノデ、ソレヲミテオモシロクオモヒ、古老ニハカリ、キヤクヲツクツテ、12月ニ内務省カラキヨカアリ。報徳社ヲタテ之ニキフシタ。[/]実測610町歩アリ。今ホートク社ガ名主デアル。[/]バツキンケイ以上ノケイニシヨセラレタモノハ除名セラレルコトニナツテイルノデ、各自甚ダ注意シテイル。[/]毎年一月ニソーカイヲヒライテ、ケツサンホーコクヲスル。[/]ツミタテ金3万円余。[/]ドダイ金ガ社ノキホンキン。山林ナドコレ。[/]善種金、毎月レイカイデツンデユク。元金ハイクラドンナコトアツテモハラハズ。リシハ善報金トシテ分ツ。[/]他村移住ノモノハ、ソノママオイテユカネバナラヌ」とある(同前:38)。
つまり明治41(1908)年12月に報徳社を起こして山林610町歩をこれに寄付し、規約を作って共同管理するようにした。これにより、村の風儀が改良されるとともに、積立金は貧困者の救済や病人の手当に融通されるようになったという。調査ノートには「生活ハ安定。赤貧者ナシ。村ニ扶助規定ガアツテ、ソレデホジヨシテイル」(同前:49)、また「病人ナドアルトキナドハ、ミナホートクシヤガ金ヲ貸シテクレル」と書かれている(同前:50)。
この報徳社を起こしたのは、八幡村樽床で宿を営んでいた後藤吾妻だった。前掲の記録は後藤からの聞取りが大部を占める。宮本は「土と共に」のなかで、「話題も豊富な人であつたが、つつみかくしのないのがじつにうれしかつた。村の恥になるやうなことさへ、それが学問の為になるものならと言つて話された」と述べている(宮本1943:242)。そして、「周囲から軽んぜられた村が今は羨まれている。このやうにしてそれぞれの村は、それぞれのよき指導者や村人の伝統によつて、少しづつ住みよくされて行きつつあるのである」と書いている(同前:249)。
なお、樽床の集落は昭和33(1958)年、樽床ダムの建設に伴いダム湖(聖湖)の下に没した(写真2)。宮本は同年6月に広島県文化財専門委員に就任し、同地の「樽床・八幡山村生活用具」を国の文化財にするよう、指導的助言を行う。同年7月14・15日には樽床を再訪し、八幡の役場で民具を視察している(毎日新聞社2005:117-118)。その時に書いた紀行文が「芸北紀行」として『庶民の発見』に収録されている。そのなかで宮本は、昭和14年の旅で見た中門造といわれる曲り家形式の民家に注目し、「それは北陸から東北地方にかけて分布している中門造と同系のもので、中門の部分に厩がある。中国山脈には点々としてこうした形式の民家が見られたというが、あるいは樽床がその西端ではないかと思っている。峡北館ももとは中門造であったというが、屋根がくさりやすいので中門をとってただの平入にしたという」と書いている(宮本1961:144)。この点は調査ノートでも確認できる。「モト馬ガ多カツタ。[/]チユーモン[中門]ガモト多カツタ。ヤネガモテヌ。モトミナチユーモンデアツタ。[/]馬ノイルトコロノマヘニキマツテアツタ。[/]入口ニヒサシヲツケル」と書かれている(板垣編2025:42)。
中国山地の物質文化には、東北・中部・北陸地方と共通するものがあり、宮本は特に日本海側からの文化の流入・定着を考えていた(宮本1961:148)。これに加え、筆者は九州地方に見られる文化要素との共通性にも注目したい。この点については稿を改めて述べる。(つづく)
引用参考文献
・板垣優河2024「縄文時代植物採集活動の研究」博士論文、京都大学
・板垣優河編2024『宮本常一農漁村採訪録26 昭和14年中国地方調査ノート(1)』、宮本常一記念館
・板垣優河編2025『宮本常一農漁村採訪録27 昭和14年中国地方調査ノート(2)』、宮本常一記念館
・毎日新聞社2005『宮本常一写真・日記集成』上巻
・宮本常一1942『出雲八束郡片句浦民俗聞書』(アチックミューゼアムノート第22)、アチックミューゼアム
・宮本常一1943『村里を行く』、三國書房
・宮本常一1961『庶民の発見』、未來社
・宮本常一1976『中国山地民俗採訪録』(宮本常一著作集第23巻)、未來社
