016
昭和14年中国地方調査ノート その15 住まいの形
資料紹介|2025年8月3日|板垣優河
宮本の民家論
宮本が住まいについて論述した書(未完の原稿を含む)は大きく分けて三つある。一つ目は『村の社会科』として昭和23年に昭和書院から発行し、昭和28年に改題して筑摩書房の中学生全集に収められた『日本の村』である(宮本1953)。二つ目は共同通信社の依頼を受けて執筆した「日本人の住まい」であり、その原稿は昭和43年1月には出来上がり、同年から地方紙に随時掲載されていたようである。三つ目は200字詰め原稿用紙417枚からなる未完の原稿で、『双書・日本民衆史』の一冊として予定されていた『すまいの歴史』の原稿ではないかと推測されるものである。このうち、二つ目と三つ目は平成19年に『日本人の住まい 生きる場のかたちとその変遷』として出版されている(宮本2007)。
そのほか、『岩波講座日本歴史』第23巻に発表した「民衆生活様式の変遷」では多くの頁を割いて衣食住のうち住生活の変遷を概観している(宮本1964)。また昭和40年頃、慶友社から『民具辞典』の刊行が計画され、宮本は住用具と農具の項を埋めるべく執筆を進めていた。この計画は結局立ち消えとなるが、宮本の執筆分は日本観光文化研究所の『研究紀要』4に「民具解説抄」として公開されている(宮本1983)。
一連の著作を通読して思うのは、宮本の民家論は、民家を生態学的条件と社会的条件のなかで実際的に位置付けようとするものであり、あくまでも生活を捉えるための手段として民家を観察し、説明しようとしていたのではないか、ということである。
宮本が早くから日本人の住まいに関心を持っていたことは、以下に示す中国地方の調査ノートからもうかがえる。
家の間取り
宮本が昭和14年に中国地方各地で撮影した写真を見ると、集落内における家々の分布には差異のあることに気付く(写真1・2)。海岸部に位置する島根県八束郡恵曇村片句(現松江市鹿島町)などの漁村は瓦屋根の二階家が多く、土地が狭いので家々は重なり合うように分布していた。一方、島根県邑智郡田所村鱒渕(現邑南町)をはじめとする農村は草屋根が多いものの比較的広く住みなしており、家の前は広場で、主家の横には納屋、その反対側には倉があり、家と家の間には相当の間隔があった。家々が立地する地理的条件や主たる生業基盤によって屋敷の取り方が相違したことがうかがえる。
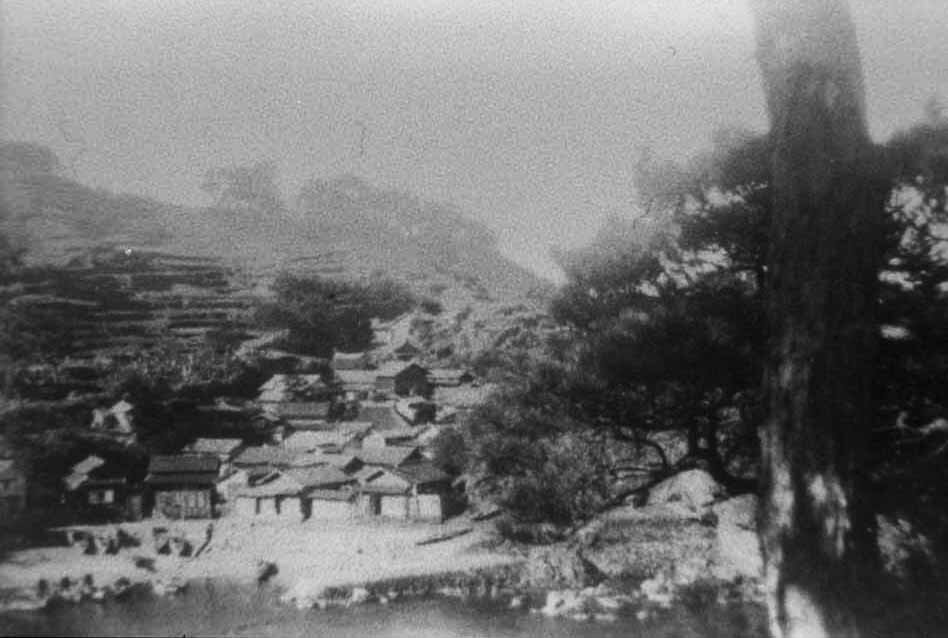

調査ノートには簡単な家の間取りが描かれている。写真3は恵曇村片句のものである。付近には「主人夫婦ハ本ザシキ、老人ハヘヤ、三ジヨーナドニヤスム。[/]ワカ夫婦ハヘヤズミ。[/]ナヤノニカイニヤスムモノアリ」との説明がある(板垣編2024:70)。『出雲八束郡片句浦民俗聞書』にはこの図を清書したものが掲載されている(宮本1942:23)。主家は田の字形の間取りで、「オモテ」には普通神床と仏壇があり、主人夫婦の寝室として利用された。その隣の「ヘヤ」は年寄りや若者の寝室として利用される。土間に接する「ナカノクチ」と「ダイドコロ」は昼間使用するところで、後者には囲炉裏が切られていた。「土間」と「ナガシモト」の間にはレンジ格子を入れてある家が多いが、これは入口から奥の台所が見透かされぬようにするためのものである。主人夫婦が「オモテ」にいる場合(所帯を息子に譲っていない場合)、息子夫婦は納屋や主家の2階に寝泊まりすることになる。これを当地域では「ヘヤズミ」と称していた。いずれにしても、家の間取りが比較的簡単なのは、その家が一夫婦を中心とした居住形態をとっていたからである。中国地方ではこのような簡単な間取りをもつ家が多かった。
また、調査ノートには田所村鱒渕の田中梅治家の間取りが描かれている(写真4)。『中国山地民俗採訪録』にはこれを清書した図が掲載されている(宮本1976:65)。同書によると、田の字形を構成する4間はいずれも8畳で、どの間にも囲炉裏が切られていたが、「ダイドコロ」以外のものはヤグラを置いて炬燵にしていたという。「カムデエ」には仏壇があり、普通はここへ特別な客を迎え入れた。「オモテ」には一般の客を入れた。老夫婦がいて、隠居部屋がない場合はここが老夫婦の寝間にもなった。「ナンド」は主人夫婦の寝室として利用された。「ダイドコロ」は「カツテ」とも「チヨーダイ」とも称し、ここで食事をとった。「ニハ」は土間のことであり、カラウスを置いて仕事場として使用した。ここには「ツケモノベヤ」(漬物部屋)というものもあった。「ツリヤ」には水屋がある。「ドザウ」(土蔵)は2箇所にあり、一つは穀物貯蔵場、いま一つは醤油や家具の保管場で、その2階は書斎として使っていた。なお、調査ノートの間取り図には示されていないが、『中国山地民俗採訪録』に掲載された図には「フロバ」の左に別棟で納屋が描かれている。これは便所や物置、牛小屋として使用されていたもののようである。また「カド」と称する庭の向こう側には道に接して石垣をつき、道に降りるための石段も設けられていた。
間取り図からうかがえる生活
「ナンド」は納戸と書き、一般的には物をしまっておく部屋のことをいうが、その部屋を拡張して中で寝ることもあった。西日本で主人夫婦の寝室を「ナンド」というのは、もとはそこが家財をしまっておく部屋だったことを示す。そして、この寝間が基本的に一つであり、寝間を中心にして家が形成されてくることは、単一家族居住が一つの制度として存在していたことを物語るものではないかと宮本は考えていた(宮本2007:105)。その場合、親は息子が嫁をもらうと寝間を息子夫婦に譲って隠居することになるし、譲らなければ息子夫婦はしばらくの間「ヘヤズミ」をすることになる。西日本ではそうした居住形態をとるところが多かった。
また、「ニハ」は土間のことであり、特に稲作農家にとっては稲扱きや籾擦り、精米などをするのになくてはならない空間だった。宮本が昭和27年11月に訪れた石川県鳳至郡能都町鶴町(現能登町)の的場家は、10町歩ほどの田地を大勢の家族や奉公人を使って手作していた旧家だが、その土間は20坪ほどあり、そこに千歯を何台も据えて稲扱きをしたという(宮本2007:43)。宮本は「民衆生活様式の変遷」のなかで、「一般民衆がどうして床張りと土間の両方を必要としたかということは、一般民衆が生産者であったことと深い関係をもつ。生産者には生産のための作業場が必要である。とくに農耕にともなう屋内作業の多くは土間が利用せられたし、また牛馬の飼育も土間でおこなわれた。つまり農家は日常単に起居する場であったばかりでなく、作業場としても重要な意味をもっていた」と述べている(宮本1964:130)。ここには民家が消費生活だけでなく、生産生活を営むための場でもあったとする宮本の民家観がよく表れている。
ただし、畑作地帯では土間が狭い家も少なくなかった。特に焼畑出作りをしていたところでは、出作り小屋でヒエなどの収納や調整作業を済ませてしまうため、土間が狭かった。写真5は吉野西奥調査ノートに描かれた奈良県吉野郡大塔村篠原(現五條市大塔町)の家の間取りである。「ウスヤ」という幅狭なスペースが土間である。調査ノートには「コナシベヤハナイ。ムギナドハ、カハラデコナス。[/]ヒエナドモカハラデヤル」と記されている(田村・徳毛編2019:114)。篠原は土地が狭く傾斜が急なため、そもそもの屋敷の幅が狭く、物干し場さえ確保できないほどだった。調査ノートに描かれた間取り図の上方には、「イシガキノ下ニハゼアリ」「スギ皮ノヤネヲフク」と書かれている。ここでは急斜面に石垣をついて平坦面を作出し、その平坦面に家を建て、石垣の外側にハゼ(物干し)を設置していたのである。写真6は宮本が昭和43年10月に同地で撮影したハゼ場で、石垣の上には庭を確保するために板を張り出しているが、その板が同時にハゼの上屋根にもなっている。ハゼには初夏は麦、夏はソバとダイズ、初秋はトウモロコシなどをかけたが、そうした作物の調整はたいてい屋外で行ったという(宮本2007:74-76)。

これに比べると、田所村鱒渕の田中家に占める土間は広い。ハゼについても、「ナランデハゼヲタテルトキハ、二間クライオク。之ヲミヨートハデトイフ」とあるので(板垣編2024:124)、干し場も十分に確保できたようである。そして付属施設の配置からも、この一軒の家がさながら自給的農業工場のようなかたちで機能していたことがうかがえる。
そのほか、家の間取りは示されていないが、広島県山県郡八幡村樽床(現北広島町)では厩(馬屋)が一つ屋根の下にある家が見られたという。調査ノートには「モト馬ガ多カツタ。[/]チユーモン[中門]ガモト多カツタ。ヤネガモテヌ。モトミナチユーモンデアツタ。[/]馬ノイルトコロノマヘニキマツテアツタ。[/]入口ニヒサシヲツケル」とある(板垣編2025:42)。中部地方や関東地方では土間を挟んで座敷の反対側に厩を設けることが多かったが、東北地方では家の表、土間の前に凸状に張り出すような格好で厩を設けることが多かった。これを中門造り、あるいは曲り家と称した。
宮本は昭和15年11月に主としてオシラサマを調べるために東北地方を歩いたが、その際に泊めてもらった秋田県鳥海山麓の農家の印象について、『日本の村』では次のように記している。「一軒の百姓家をたずねて、宿を貸してもらおうと思って入口の戸をあけますと、眼の前に馬が一頭、横になって立っています。入口から声をかけてわけをはなしますと、とめてやるから入ってこいといいます。馬がいますのでためらっていますと、その家の人は馬の腹の下をくぐってこい、というのです。ぼとぼとにぬれてリュックサックを背おっている私は、ウマヤのしきわらの上を四つばいになって家のなかにはいったのでした。馬はじっとして、何もしませんでした。ここでは、馬がまったく家族の仲間入りをしているのでした」(宮本1953:28-29)。
同書で宮本は、こうした中門造りの家は「案外ひろく各地に見られる」とも書いている(同前:27)。『庶民の発見』では昭和14年の中国地方の旅で見聞した家は北陸から東北地方にかけて分布している中門造りと同系のもので、「中国山脈には点々としてこうした形式の民家が見られたというが、あるいは樽床がその西端ではないか」と述べている(宮本1961:144)。
家屋根の形
写真7は昭和14年11月23日に宮本が田中家の外観を撮影したものである。不鮮明だが、先述した「カド」の方から主家を写したものと思われる。注目したいのは屋根の形であり、多段階に葺かれていることが分かる。調査ノートにも田中家の屋根が描かれており(写真8)、次のように記されている。「ヤネヲアサガラデ葺ク。[/]10年バカリハモツ。アサガラハジブンノ家デツクツタモノヲタメテオク。ソレデ十分アル。アサガラノ少イトコロハワラヲツカフ。[/]ヤネヤガ大抵ソノブラクニイテ、ソレガ葺ク。[/]素人中ノ上手ナモノデ、ソノ人ガフイテ、他ガテツダフ。タイテイソノ日ニフイテシマフ。[/]オガラハ天井ウラヘアゲテオク。[/]コムギワラヲ使用スルコトモアル。[/]カヤハスミダハラヲツクルニ用ヒルガ、村ノセイサンデハ、スミガツツミキレヌ。カヤヲ以テヤネヲフクコトハ出来ン」(板垣編2024:113-114)。

先の記事で紹介したように、田所村ではアサを栽培しており、その残滓を利用して屋根を葺いた。屋根の図を見ると、この屋根は水はけを良くするための「シノムネ」を持つことによって多段階になっている。また棟は傷みやすい部分なので、ここには「ハコムネ」と称し、限定的に瓦を置いていた。なお、一般的に草屋根の場合、その耐用年数はカヤ葺きなら25年、麦藁葺きなら6年、藁葺きなら2~3年程度とされる(宮本・財前1974:41)。カヤが不足するところではカヤと麦藁が併用されたが、田所村ではアサを用いていた。
ついでに、江戸時代までの農家は一般に瓦葺きが許されていなかったが、明治になると瓦で葺いてもよいことになり、瓦屋根が急速に増えてくる。しかし、重量のある瓦をのせるには屋根裏構造の変更が必要であり、その技術は堂宮大工が持っていた。宮本の郷里がある周防大島長崎はそうした大工を多く輩出したところで、草屋根から瓦屋根への移行が比較的早く進んだ。長崎の場合、明治20年頃には瓦屋根の家は1戸しかなかったが、明治40年代にはほとんどが瓦屋根に変わっていたという(宮本・岡本1982:77)。この大工たちは「長州大工」と呼ばれ、大島から四国へ渡って仕事をしたが、そこでも堂宮建築の技術を応用して民家の建築や屋根替えをした。このことから、宮本は草屋根が時勢の変化によって何となく瓦屋根に変わったのではなく、東北地方で遅くまで草屋根が残ったのも、屋根組技術を持った大工が少なかったからではないかと推測している。「文化は一様に一斉に進んでいくのではなく一人一人の意志と技術を持つ人びとのからみあいによって進んでいったものである」と述べている(宮本1979:43)。
宮本は家の間取りや屋根の形からその地域や家々で営まれていた生活や生産活動を読み取ろうとしていた。そして調査先での実際的な見聞をもとにして、この記事の冒頭で述べた民家論を提示していたのである。(つづく)
引用参考文献
・板垣優河編2024『宮本常一農漁村採訪録26 昭和14年中国地方調査ノート(1)』、宮本常一記念館
・板垣優河編2025『宮本常一農漁村採訪録27 昭和14年中国地方調査ノート(2)』、宮本常一記念館
・田村善次郎・徳毛敦洋編2019『宮本常一農漁村採訪録21 吉野西奥調査ノート』、宮本常一記念館
・宮本常一1942『出雲八束郡片句浦民俗聞書』(アチックミューゼアムノート第22)、アチックミューゼアム
・宮本常一1953『日本の村』、筑摩書房
・宮本常一1961『庶民の発見』、未來社
・宮本常一1964「民衆生活様式の変遷」『岩波講座日本歴史』第23巻、岩波書店、109-172頁
・宮本常一1976『中国山地民俗採訪録』(宮本常一著作集第23巻)、未來社
・宮本常一1979「一枚の写真から12」『あるくみるきく』147号、近畿日本ツーリスト 日本観光文化研究所、42-43頁
・宮本常一1983「民具解説抄」『研究紀要』4、日本観光文化研究所、3-97頁
・宮本常一2007『日本人の住まい 生きる場のかたちとその変遷』、農山漁村文化協会
・宮本常一・岡本定1982『東和町誌』、山口県大島郡東和町
・宮本常一・財前司一1974『日本の民俗 山口』、第一法規出版
